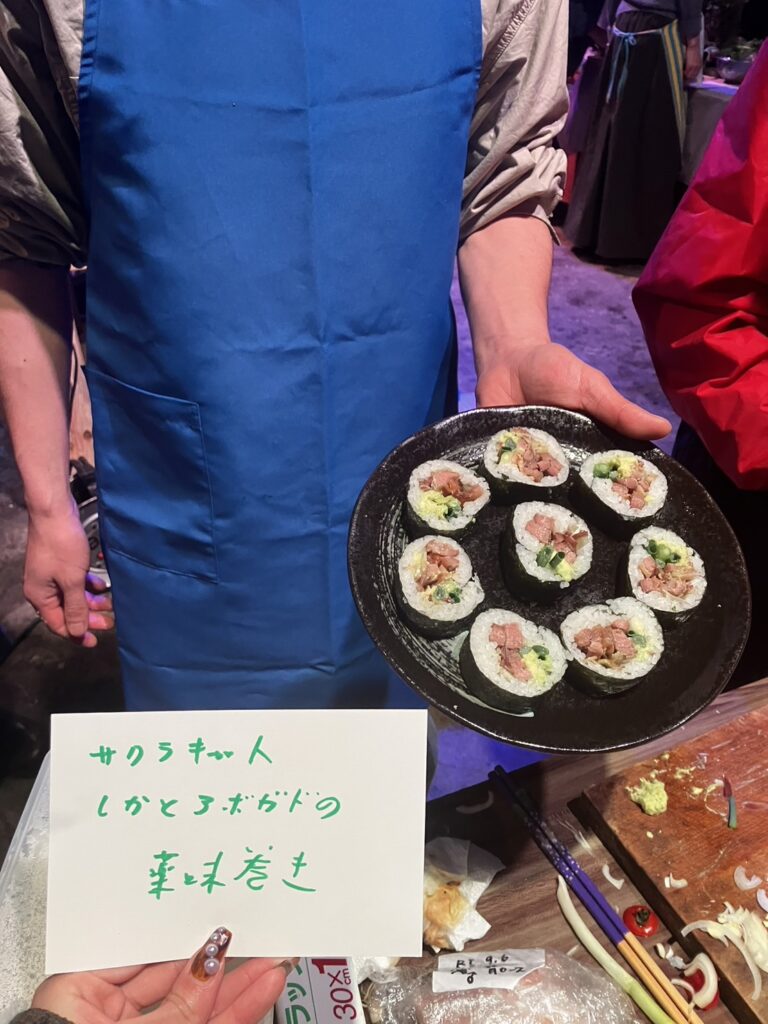実習風景~その100~
こんにちは!京都寿司アカデミーの永井です。 今日は、カマス塩焼き、イワシ握り、タコ波切りの3つを紹介します。まず、カマス塩焼きは、脂の乗ったカマスをシンプルに塩で味付けし、香ばしく焼き上げます。焼き加減がポイントで、皮はパリッと、中はふっくら仕上げることで、魚本来の旨味を引き出します。カマスの繊細な風味が口いっぱいに広がります。次に、イワシ握り。新鮮なイワシを使用し、程よく締めることで魚の持つ旨味と脂を際立たせます。シャリとのバランスも大切で、少し濃いめのタレをかけることで、イワシの風味がより豊かに感じられます。手軽に楽しめる握りですが、技術と工夫で一層美味しく仕上がります。最後にタコ波切り。茹でたタコを包丁で独特の波状に切り、食感を楽しむ一品です。タコの弾力と風味が生きた切り方で、見た目も美しく、味わいも深い。少しの工夫で、普段のタコとは違った楽しさを提供します。これらの料理は、寿司の技術だけでなく、素材を生かすことの大切さを再認識させてくれたと思います。